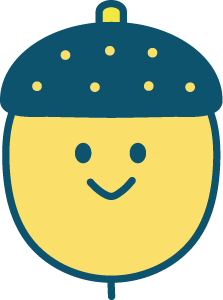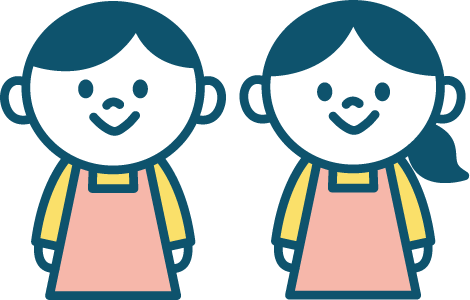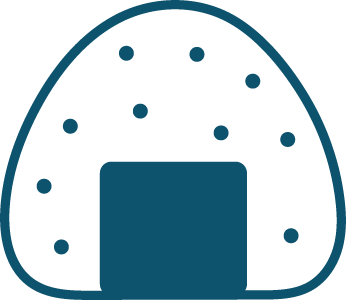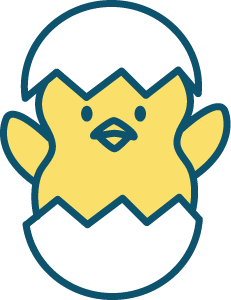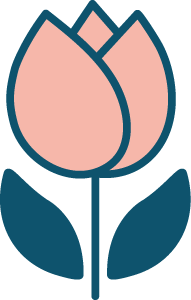昨年に引き続き、親子レクとPTA総会の後、パネルディスカッションが開催されました。
司会進行は、保護者であり卒園生でもある新垣さん。今年も和やかな雰囲気の中でパネルディスカッションが行われ、園の教育の特徴や子育てに関する実感が数多く語られました。


佐久田園長:「提示」が生み出す子どもの集中力

園長先生は、クララ幼稚園が大切にしているモンテッソーリ教育の「提示」について次のように話しました。
「モンテッソーリ教育では、子どもは言葉で説明するよりも、動作でやって見せたほうが捉えが早いと考えます。これを“提示”と呼びます。クララ幼稚園の教師は、2年間モンテッソーリ養成コースで学び、教具の使い方を一つひとつ習得しています。その目的や、子どもの発達段階に応じた提示の仕方をしっかりと把握しているのです。
実際に『見ていてね』と声をかけて、教師がゆっくり順序立てて提示すると、子どもたちはじっと集中して見ます。その後、子どもたちは自分で“お仕事”を始め、順序よく、何度も繰り返します。やり遂げていく過程の楽しさが脳にインプットされ、この経験が小学校、中学、高校、大学、そしてその先の人生にまで影響していくのです」
嶺井主任:「秩序」と「選び」が育む安心感と意欲

主任の嶺井先生は、クララ幼稚園で大切にしている「秩序」と「選び」について説明しました。
「子どもたちは登園すると、まずカバンから出席カードを出し、カバンを片付けるといった順序があります。園内には、いつも同じ場所に同じお仕事(教具)があり、その中からやりたいことを選びます。そして使い終わったら次に使う子のために片付ける。こうした“いつもの順序・いつもの場所・きまったお約束”が、幼稚園でいう『秩序』です。この秩序が守られていると、子どもたちに安心感が生まれるのです。
これは家庭でも同じことが言えます。順序が急に変わったり、早くなったり遅くなったりすると、子どもは不安や迷いにつながります。家庭でもできるだけ秩序を保つことで、子どもの心が安定し、『やってみよう』『できた』『もっとやってみたい』という意欲につながるのです。
さらに園内では『選び』が数多くあります。どこで遊ぶのか、当番は何をするのか、発表会ではどの役をするのか。子ども自身が選ぶ経験を重ねることで、卒園後も自分のやりたいことを見つけて成長していくことができます。保護者の皆さんには、焦らずに子どもが何を選ぶのかを楽しみながら見守っていただけたらと思います」
保護者の体験談①:伊集さん「大泣きから安心へ」

保護者として最初に発言した伊集さんは、長女の入園当初の様子を次のように語りました。
「長女はもともと地元の保育園に通っていましたが、黒いクレヨンで黒い絵しか描かなくなり、不安に感じてクララ幼稚園へ転園しました。最初は毎日の登園が大泣きで、本当に大変でした。でも年長のパートナーさんのおかげで、2学期ごろには安心して登園できるようになりました。年中さんになった頃には幼稚園が楽しいと感じられるようになり、絵も普通に描けるようになりました。クララに通わせて本当に良かったと思っています」
保護者の体験談②:大城さん「親子二代のモンテッソーリ教育」

大城さんは、自身の幼少期と子育てを重ねて振り返りました。
「私はクララ幼稚園と同じカトリック学園の愛児幼稚園で、モンテッソーリ教育を受けました。その楽しかった思い出があったので、自分の子どもも自然な流れでクララに入園させました。3人の子どもたちがお世話になり、子育てもスムーズにできています。卒園した中学1年と小学4年の子も、それぞれ個性はまったく違いますが、それもまたクララの教育の良さを感じています」
保護者の体験談③:川上さん「家庭でも生きる“選び”」

川上さんは卒園生であり、クララ幼稚園の元教師。現在は子育てに専念している立場から語りました。
「私は家庭の中で、幼稚園で培った教育をどう活かすかを考えてきました。小学5年生の息子は外に出ることが少なく、私はゲームやSNSから少しでも離れ、自分の好きなことを見つけ、家族の時間を楽しんでほしいと思っていました。そんな時、学校で新聞スクラップの授業があり、息子が天然記念物に興味を持ったんです。それをきっかけに一緒にクイナを見に行きました。そこから探究心が広がり、親子の会話も増え、あたたかさを感じるようになりました。
それ以降は出かける際も、親が全てを決めるのではなく、幼稚園で学んだ『選び』を活かして、行き先やスケジュール、準備を息子自身に考えてもらうようにしています」
佐久田園長が語る「母親としての体験」

新垣さんからの問いかけで、佐久田園長が一人の母としての体験を語り、会場を大きく引き込みました。
「私の長男は幼稚園の頃、本当に慌てん坊でした。卒園後、小学2年のときに自分から少年野球に入りたいと言い出しましたが、全くボールが投げられない。それでも全体を見る力があると言われ、キャッチャーを任されました。コーチから『この全体を見る力、どうやって育てたの?』と尋ねられました。
この言葉、クララを卒園した子の保護者がよく言われる言葉です。『自分のことは自分でする、自分で調べる、人にはやさしい、問題解決をちゃんとしていく。この子はどうやって育てたの?』と。それでみんなこう答えるんです。『クララで育ったかな』って。私もコーチから尋ねられた時、クララの教室を思い浮かべました。室内にいろんな教具があって、それを選び、使い終わったら元の場所に戻す。私も答えました。「クララで育ったかな」って。
息子は野球に熱中し、勉強は後回し。小4の頃、私が『塾に行く?』と聞くと『行かないで頑張る』と答えました。結局中学3年まで野球を続け、部活が終わったころ、自分から『塾に行きたい』と言い出し、すでに行く塾も選んでいました。塾がない日も毎日自習室に通い、集中力を発揮して成績は一気に上位へ。『席次10番以内に入る』と自分で決めてやり遂げたのです。
今思えば、もし私が無理に塾へ行かせていたら、反発し不満ばかりの子になっていたかもしれません。親が子どもの“選び”を無視して自分の思うようにさせようとしても、子どもは自分の人生に納得できません。自分で選び、責任を持つからこそ、反抗もなくなり、集中して成し遂げる力を身につけていくのだと思います。
私自身も、息子の“選び”に不安を感じたことは何度もありました。でも我慢し、意識を変えることが必要でした。子どもの集中や選んだ道を妨げないように見守る——親の役割はそこにあるのだと思います。32歳になった今の息子の姿を見て、改めてそう感じています」。
会場の声:「敏感期を捉え、長所を伸ばす」


会場から、自身も卒園生である保護者からの発言もありました。
「子どもがやりたいことを選べるのが良いと思います。教師が専門的な知識で敏感期を捉え、適切に声をかけてくださるので、子どもがぐんと伸びるのを感じます。ある日、子どもが折り紙を見て『これって鈍角だよね』と言ったことがあり、驚きました」
別の保護者はこう続けました。
「自分でお仕事を選んでやるというのは昔も今も変わらず続いていると思います。それは私自身にも身についていて、今の仕事にも生きています。娘も入園して1年。旅先の温泉でいったんは浴槽に浸かったのですが、シャワーの水が漏れ出ていたため止めにいき、ついでに椅子をきれいに並べ始めました。家で教えたことはないので、クララで学んだことを自分で応用したのだと思います。これからの人生に必ず生きていくと確信しています」
パートナー制度について
最後に、アンケートから寄せられた質問「パートナー制度について園児たちはどう捉えているのか」に対し、嶺井主任が答えました。
「不安で登園した子も、年長のパートナーさんが迎えに来てくれることで安心して教室に入れます。トイレや食事の場面でも寄り添い、外遊びでは一緒に戻ってきてくれる。泣いていたらそばにいてあげる。そうした姿が子どもたちの安心につながっています。
一方で、年長の子たちにとっても大きな学びになります。頼られることで自信を持ち、どうやったら相手に伝わるか、どうしたら安心してもらえるかを一生懸命考える。その経験の中で控えめだった子が元気な声を出せるようになったり、積極的にお世話をするようになるのです。これこそ縦割り保育の良さだと思います」
まとめ
クララ幼稚園で培われる「自分で選び、やり遂げる力」は、子どもたちが卒園してからも人生の土台となっていることが、多くの声から浮かび上がりました。保護者や教師、そして園長自身の体験談は、子どもを信じ、選びを尊重して見守ることの大切さを改めて教えてくれます。